健康食品 本物にこだわった自然食品、健康食品をご案内。自分が飲んで、食べてお気に入りの健康食品をご紹介
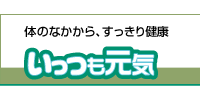 |
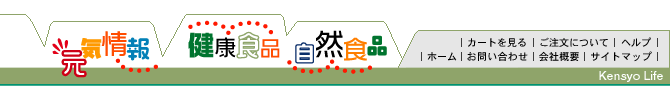
|
■ びわの種と炒り玄米粉の 「びわっこ」
|
|||||||
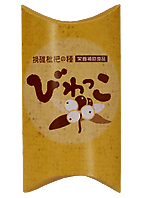
|  【補助食品】 昔からびわは、漢方薬などでも知られている果実。そのびわの種子を丹念に石うすでひき、無農薬の煎り玄米をまぜた、健康維持に効果的な食品です。 近年びわ療法としても注目を集めています。疲れやすい方のヘルシーライフを応援します。 |
インド、中国でも古くから民聞療法として、煎し汁が健胃整腸、夏の清涼剤に、また温灸などさまざまに利用されてきました。最近ではガン予防にも効果があるといわれ注目されています。
ビワは3000年の昔からそのすぐれた薬効が知られていました。インドの古い教典には、ビワの木は「大薬王樹」、葉は「無憂扇」とあります。 「薬効のある植物はいろいろありますが、もっとも効果のあるのはビワの木で、その枝、葉、根、茎のすべてに薬効のある成分が含まれている」という意味のことが書かれ、 さらに「水や密、牛やヤギの乳に混ぜて服用してもよし、香りをかいでも、体にあぶっても、手に触れただけでも生けるものすべての病気を治す」と説かれています。 中国の古い漢方の書、『本草綱日』でも「胃を和し、気を下し、熱を清し、諸毒を解し、脚気を療ず」と説明されています。 古くから中国の家庭の保健薬として愛用されており、疲労回復、夏ばて、カゼの予防などにもつかわれてきました。 また〃枇杷葉湯〃は今でも広く飲用されています。 このように仏教伝学として出発したビワの葉の療法が日本に伝わってきたのは奈良時代で、施薬院にはビワの葉療法を用いた事跡が今でも残っています。 そして各地の寺にビワの木が植えられて村人たちの病を救ってきましたが、大正時代になってもある寺に20万人以上の難病、奇病の人が全国から集まってきたという記録もあるほどです。 ビワの種の成分はブドウ糖、果糖、マルトース、デンプン、デキストリン、酒石酸、リンゴ酸、アミグダリン(ビタミンB17)、タンニンなどであります。 特にアミグダリンは重要な成分で、これを精製してレイトリルという薬品をもつくられています。 アミグダリン(ビタミンB17)の豊富なビワの種 アメリカのエルネスト・T・クレブス博士はこのビワの種からレイトリルという物質を抽出しましたが、これがビタミンB17で、酵素とともに働いてガン綱胞の破壊作用を行うことが明らかになったり、 レイトリルはアメリカで抗ガン剤として治療に使われています。 アミグダリンは体内で血液の酸性とアルカリのバランスを整えて血液を浄化します。 体内でのこの化学変化が炎症を治癒する作用をするので自然治癒力を復活させ痛みを止めたり、消炎、制ガンなどの働きもすることになります。 肩こり、腰痛、心臓病、高血圧、肝臓病などの成人病や頭痛、神経痛、婦人病、自律神経失調症、切りきずや各種皮膚病、健胃整腸、利尿効果など実に広範囲に及ぶ効用が万病に用いられるゆえんであります。 |
|
アルファルファと納豆菌シリーズ
昭和58年より健康を愛する方に、愛され続けています!
「スーパーベジタブル」は、毎日の野菜不足を補い、「納豆菌シリーズ」は 納豆菌、乳酸菌で善玉菌を強化。セットで飲むと相乗効果が期待できる!腸の中の善玉菌を元気にし、健康の基礎つくりをしっかりサポート!




