ミネラル栄養学 今なぜミネラルなか?ミネラルとは
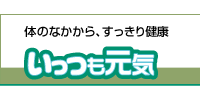 |
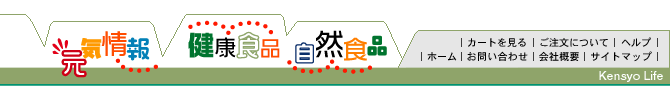 |
▼ 今、なぜ、ミネラルか No.1
|
| ▼ 今、なぜ、ミネラルか 2 |
| 健康産業流通新聞 平成10年5月21日(木曜日) FLI食と生活情報センター所長 藤眞氏 |
| ■ミネラルは人体の潤滑油 水に溶かし,効力を発揮
|
| 現代は、なぜミネラル不足といわれているのでしょうか。ミネラルは人体の潤滑油みたいなもので、他の栄養素を運んだり、酵素の一部として欠かせない働きをしています。ミネラルの媒体は「水」であり、水の中で溶け込まれて初めてその効力を発揮するものです。
人体に必要必須のミネラルはプラスのイオン(アルカリ金属)である(1)カルシウム(2)マグネシウム(3)カリウム(4)ナトリウムの四種とマイナスのイオン(酸性金属)である(1)リン(2)塩素(3)イオウの3種、計7つのイオンで、人体の酸と塩基(アルカリ)の平衡を保っているものです。それにアルカリ金属を運ぶ重炭酸や有機酸が加わって体液のバランスを保っています。どちらが多くなっても入体は生命の維持が難しくなり、死を迎えます。 アルカリ金属が多くなってしまった状態をアルカローシス、酸性が多くなってしまった状態をアシドーシスといって、もはや病的状態となります。そして人体はPH7.4に保たれ、この内部環境の安定性の存在と維持を生体恒常性(ホメオスタシス)と呼んでいます。現代は内外の環境が崩れ、このホメオスタシスが正常に機能しなくなっています。 生命維持必須ミネラル7種の他に、微量必須のミネラルが15種あげられ、計22種ものミネラルが人体には必要で、欠けると体内のメカニズムがスムーズに働いてくれません。人体の体重の60~70%は水分ですが、単なる水ではなく生命維持のために必要必須のミネラルが溶けている電解質の液体となっています。 そしてその液体は、細胞の中の水、細胞内液と細胞の外にある水、細胞外液のふたつがあり、細胞外液は血漿水と細胞間質液に分かれます。体重の50%近くが細胞の中の水としてあり15%内外が間質液、5%が血漿という分散をしています。細胞の内外は細胞膜でへだてられ、その内外を結ぶトンネルをイオンチャネルと呼び、そのトンネルを通じて水とミネラルが出入りして移動することにより細胞は動いているものです。そのため人体にとってミネラルバランスを保つということは、生命を維持することに他ならず食べた物によってそのバランスが保たれるのは当然のことです。 食べる物のミネラルバランスが悪ければそのバランスが崩れるのは当然なことで、現代は食べる物のミネラルバランスが悪くなってしまった時代といえます。なぜミネラルバランスが悪くなってしまったかといえば、生活することの循環が人口過剰で変わってしまったからに他なりません。日本の土壌は火山灰地帯で、田畑にするためには土づくりから始めないとよい作物ができません。そのため堆肥作りは次かせないものでした。 雑木林の枯れ葉、牛、馬、豚、鶏の糞や、人糞を発酵して堆肥に変え土にもどし、また作物を作るという循環を繰り返していたため農業が発展したのです。江戸時代までは人糞は海に捨てずに土壌にすべて還元されていました。ところが下水が完備され、衛生的になった反面、その還元がまったくストップしてしまったのです。 野菜に回虫が多いのは人糞の下肥のためと廃止されたものです。昭和20年代のことですが、肥料は三大栄養素、リン、チッソ、カリで十分野菜は育つと化学肥料を大量に散布し始めた時でもあります。紀元前からの方法がくずれてしまったものです。リン、チッソ、カリの片寄った栄養素では、今まで培われてきた土壌には2~3年の間大豊作を与えましたが、当然微量元素が不足してきて、よい作物がとれず、病気が多くなってきてしまいました。 そこで農薬の大量使用が始まったのです。土壌を実際に分析するとリン、チッソ、カリは過剰、カルシウムも過剰、マグネシウムは畑によって過剰か不足か、亜鉛、銅、ホウ素などの微量ミネラルは不足しています。カルシウムの過剰は、土壌の見かけのPHを上げるために多量投与されている水酸化カルシウム(硝石灰)のためで、水に溶けないためカルシウムがあっても作物にまったく反映されません。 畑のミネラルバランスが片寄っている訳で、そこでとれた野菜もミネラルバランスが悪いということになります。もともと良い農産物には、カルシウム、マグネシウム、カリウムが多く含まれ、他の栄養素も多くなります。良い作物は腐りにくい、味が良い、コクがあるなど特徴があり、いろいろな作物に、秀・優・良・特級・上級というようなランクがあるのも、良くできたか、それより落ちるかの差であり、ミネラルリッチが良い作物の証でもあったのです。 |
アルファルファと納豆菌シリーズ
昭和58年より健康を愛する方に、愛され続けています!
「スーパーベジタブル」は、毎日の野菜不足を補い、「納豆菌シリーズ」は 納豆菌、乳酸菌で善玉菌を強化。セットで飲むと相乗効果が期待できる!腸の中の善玉菌を元気にし、健康の基礎つくりをしっかりサポート!



